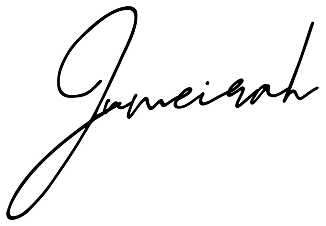
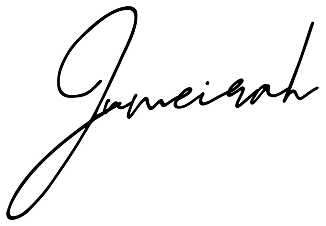
「生理痛がつらい」「更年期の体調変化にどう対応すれば良いかわからない」と感じる女性は少なくありません。こうした課題に対し近年注目されているのが「フェムテック」です。フェムテックとは、女性特有の健康課題をテクノロジーで解決する製品やサービスの総称で、生理・妊活・妊娠・更年期・メンタルケアまで幅広く対応しています。アプリやツールを活用することで、自分の体の変化を「見える化」し、適切な対策につなげられる点が大きな魅力です。市場は世界的に拡大しており、日本国内でも行政や企業の取り組みが進んでいます。本記事では、フェムテックとは何か、その意味や背景・具体的な活用方法をわかりやすく解説します。

フェムテックは、女性の健康課題をテクノロジーで解決する新分野として注目されており、社会的意義と市場性の両面で急速に拡大を見せています。
フェムテックとは「Female(女性)」と「Technology(技術)」を組み合わせた造語で、女性特有の健康課題をテクノロジーで解決しようとする製品やサービスの総称です。初めてこの言葉が広まったのは2013年頃で、生理管理アプリ「Clue」を開発したドイツの起業家イダ・ティン氏が提唱者とされています。フェムテックの対象は、生理・妊活・妊娠・更年期・性感染症予防など多岐にわたり、これまで十分に可視化されてこなかった女性の悩みに光を当てる役割を果たしています。単なるガジェットやアプリではなく、女性の生涯に寄り添うライフテック領域として注目が集まっています。
フェムテックが注目されている背景には、社会構造と価値観の変化があります。まず、ジェンダー平等への意識の高まりとともに、女性特有の健康課題が社会的に語られる機会が増えました。さらに、晩婚化や高齢出産といったライフスタイルの多様化が、妊活・更年期ケアへのニーズを高めています。こうした背景を受け、フェムテック市場は世界的に急拡大しており、2025年には世界市場規模が5兆円を超えると予測されています。日本国内でもフェムテックをテーマにした展示会や行政支援が増加しており、医療・美容・IT分野が連携する新しい市場として注目が集まっています。
フェムテックが対応する領域は年々拡大しており、医療だけでなく日常ケアやメンタルヘルスまでをカバーするのが特徴です。代表的な分野としては、生理周期の可視化を行うアプリや、高吸水ショーツなどの生理用品、排卵日予測機器、不妊治療支援ツールなどがあります。また、更年期のホルモン変化に対応する体調管理アプリや、出産後の心身のケアを行うオンライン相談サービスなども登場しています。メンタル面ではPMS(月経前症候群)による気分変動をサポートする仕組みも重要視されています。これらは女性のQOL(生活の質)を向上させる実用的なテクノロジーとして広く活用されています。
フェムテック製品は、生理・妊娠・更年期など女性のあらゆるライフステージに対応し、日常生活の質を高める実用性とテクノロジーが融合したアイテムです。
フェムテック製品の中でも特に使用者が多いのが、生理管理アプリ・吸水ショーツ・月経カップです。生理管理アプリは、排卵日や生理周期の予測だけでなく、体調や気分の記録機能も備えており、自分の体調傾向を把握するのに役立ちます。吸水ショーツはナプキン不要で使える新世代の生理用品で、肌への優しさや繰り返し使える点が好評です。月経カップは膣内に装着して経血を溜めるタイプで、長時間の使用や運動時にも安定して使えるのが特長です。いずれも日常生活に取り入れやすく、衛生面やコスト面でも利点があるフェムケアアイテムとして人気を集めています。
フェムテック製品は、女性の人生における様々な段階に応じた課題をサポートするよう設計されています。妊活期には、排卵日予測や基礎体温の自動記録ができるスマート体温計や、ホルモン分泌をチェックする尿検査キットが人気です。妊娠期には、胎動を記録できるアプリや出産準備サポートアプリがあり、医師との連携がしやすいものも登場しています。更年期には、ホルモンバランスの変化に伴う症状を可視化できるアプリや、自律神経を整えるウェアラブルデバイスが活用されています。このように、フェムテックは年齢や状況に応じたサポートを提供する点で非常に実用的です。
フェムテック製品を選ぶ際は、機能性・安全性・信頼性の3つを基準にすることが重要です。まず、アプリやデバイスは自分の目的に合った機能を持っているか確認し、必要以上にデータを取得しないものを選ぶと安心です。衛生用品であれば、素材の安全性や洗いやすさも選定のポイントになります。さらに、医療情報を取り扱う製品やアプリでは、個人情報保護の体制が整っているかも確認が必要です。実際の使用にあたっては、正しい使用方法を守り、異常を感じた場合はすぐに使用を中止し医療機関に相談しましょう。テクノロジーに頼りすぎず、自身の身体感覚を大切にする姿勢が求められます。
フェムテックは、婦人科疾患や不妊治療、デリケートゾーンのケアなど医療分野にも広がり、女性のヘルスケアを包括的に支援する存在へと進化しています。
フェムテックは、婦人科領域におけるさまざまな疾患の早期発見や治療支援にも活用されています。たとえば、生理周期を記録するアプリは、PMSや月経困難症の兆候を見つけるきっかけになります。また、排卵日予測やホルモンの変動を解析するデバイスは、不妊治療中のタイミング管理に有効で、医師との情報共有にも役立ちます。さらに、AIを活用した問診アプリは、症状の整理や通院前の情報把握を可能にし、診療の質を高めるツールとしても注目されています。デジタル技術によって、自身の身体の状態をより正確に把握し、適切な医療介入へとつなげられる点がフェムテックの大きな強みです。
近年では、フェムテック製品の一部が病院やクリニックでも活用されるようになっています。特に、不妊治療クリニックや女性外来では、排卵検査機器やホルモン測定キットを診療補助として導入するケースが増加中です。また、医師が推奨する生理予測アプリや更年期症状の記録アプリなども、診療の補足ツールとして活用されています。こうした動きに対して多くの医師は「患者の身体理解を促し、医療の質を高める」と評価する一方で、「自己判断での過信には注意が必要」とも指摘しています。フェムテックを医療と連携させることで、よりパーソナライズされたヘルスケアが実現しつつあります。
フェムテックの進化により、デリケートゾーンの健康管理もより精密かつ日常的に行えるようになっています。たとえば、pHバランスや常在菌の状態を測定できる家庭用検査キットは、膣内環境の変化を早期に把握する手段として活用されています。これらのデータはアプリと連携させて記録でき、異常があれば早めに医療機関への受診を促す仕組みになっています。また、性感染症のセルフチェック用キットも登場しており、匿名で検査から結果確認まで完了できるのが特徴です。フェムケアが日常化することで、羞恥心や面倒さから解放され、女性が主体的に体調を管理できる環境が整いつつあります。
フェムテック市場は世界で2024年に約600億ドル、日本でも多数のスタートアップが活動中で、今後の成長性や先進企業の取り組みが注目されています。
2024年の世界フェムテック市場は約602億ドル(約60.2 Bドル)、地域別では北米が市場の約46%を占めています。2025年には約662億ドルに達し、2025‑34年の年平均成長率は16%と見込まれています 。さらに別の調査では、2025年に世界市場規模が約608.9億ドル、2034年には約1,308億ドルに拡大する予測もあり、今後10年間で拡張が続く見通しです 。
日本国内には、2025年時点で約49社のフェムテックスタートアップが存在し、そのうち18社が資金調達済みです。代表的企業には、月経トラッキングアプリ「Simpluna」、妊活支援の「Lalune」、女性のメンタルケア製品を提供する「Melody International」などがあります。東京大学やUCバークレー出身者による創業もあり、国内市場における技術力や文化的視点を活かした製品投入が進行しています。
海外では、AI搭載生理・妊活アプリやウェアラブルデバイスが普及しており、例えばイスラエル発の「Livia」は月経痛を抑えるTENS機器として米国FDAなどの承認を得ています。また英国のElvieは乳房ケアや骨盤底筋トレーニング製品が展開され、日本でも進出企業との提携が進んでいます 。こうした製品は、医療機関との連携承認や法規制への対応により信頼性が高く、現地導入のモデルケースとなっています。
フェムテックは期待される一方で、誤解や制度的課題も抱えています。正しい理解と社会全体の受け入れが、今後の発展に不可欠な要素となっています。
フェムテックという言葉は生理用品のイメージと結びつきやすいですが、実際には妊活・妊娠・更年期・メンタルヘルスなど、女性のライフサイクル全体を支える技術が含まれています。そのため「フェムテック=生理用品」という誤解は、製品の活用範囲を狭めてしまう要因となります。また、男性や医療従事者がこの分野を十分に理解していないケースも多く、啓発活動が求められています。製品そのものだけでなく、背景にある女性の身体や心の課題についての教育や情報提供を通じて、社会全体がフェムテックを包括的に理解することが、活用の広がりにつながります。
フェムテックの普及にあたっては、さまざまな社会的・倫理的課題も指摘されています。特に生理アプリや排卵予測デバイスなどで取得される個人データの管理は、プライバシー保護の観点から非常に重要です。また、ジェンダー規範やバイアスに基づく設計や広告が、利用者の不信感を招くこともあります。さらに、医療行為と誤認されるような機能を持つ製品が、正確な知識なしに使われることで健康リスクが生じる可能性もあります。これらの課題を解決するためには、製品開発時の倫理ガイドラインの整備、情報提供の透明性、行政・医療機関との連携が必要不可欠です。
フェムテックの最大の価値は、テクノロジーを通じて女性自身が自分の体と向き合う機会を得られる点にあります。月経周期やホルモン変動、PMSの傾向、妊活に関する記録などを通じて、これまで感覚で捉えていた身体のサイクルをデータとして「見える化」できます。こうした情報は、体調管理や医師への相談時に非常に有効であり、自分の健康に主体的に取り組む意識を育てる助けになります。また、自分の状態を理解することで、周囲とのコミュニケーションも円滑になり、社会的な理解促進にもつながります。フェムテックは単なる商品ではなく、女性の自己決定権を支援するツールでもあります。
フェムテックは、生理や妊活だけでなく、女性の人生全体を支える重要な分野として注目されています。テクノロジーの力で女性の身体や心の変化に寄り添い、医療や日常生活の質を高める可能性を秘めています。一方で、プライバシー保護や正しい知識の普及といった課題も存在します。今後は、個人と社会がフェムテックを正しく理解し活用することで、女性が自分らしく健康に生きるための選択肢がさらに広がっていくでしょう。